博士学生やポスドクにとって、日本学術振興会(学振)の特別研究員は、ぜひとも採択されたい重要な制度です。
しかし、その選考プロセスや評価システムを正確に理解している人はそれほど多くありません。
(※正確には日本学術振興会のことを学振と略しますが、本記事では便宜上、特別研究員DC/PDの制度や申請書のことを「学振」と呼ばせていただきます。)
- 学振の審査って、何を見られている?
- 学振の選考方法とTスコアとは?
- 開示請求した学振の評価結果をどう見ればいい?
学振に採択されるためには、上記のような選考プロセスや審査基準、評価方式を事前に確認しておくのも一つの賢い方法です。
また、学振の審査結果に関わらず、そのTスコアを自己分析することで、今後に繋げることができます。
今回の記事では、学振DC/PDを目指す人に向けて、公式情報だけでは読み解きにくい選考方法や審査基準、そして分析方法について解説します。
学振の選考方法とは?
学振の選考プロセスは、決してブラックボックスになっているわけではありません。
日本学術振興会が公表している情報をもとに、4つのステップに分けて解説していきます。
①書面審査セット、審査区分表に従って申請・審査がスタート
あなたが学振の申請書を提出する際には、研究分野に応じて「小区分」を選択することになります。
例えば日本語に関する研究においては、「日本文学関連」、「日本語学関連」、「日本教育関連」といった形で小区分が分かれています。
その小区分から自動的に決定される「書面審査区分」、そしてより広範な「書面合議審査区分」という階層構造を持つ「審査区分表」に基づいて、審査が行われます。
(※詳細は審査区分表をご覧ください)
そして、実際の書面審査は適切な相対評価ができるよう、「書面審査セット」と呼ばれるグループに振り分けられます。
ここで重要なのは「あなたの申請書は、基本的には専門分野が一致していない別の申請書と比較される」という点です。
例えば、「美術史関連」の小区分を選択した場合、同じ書面審査セット「人文学1」に含まれる「哲学および倫理学関連」などの申請書と比較して相対評価されることになるのです。
後述しますが、5名の審査員のうち4名は自分と専門分野が異なっているという前提で、申請書を書きましょう。
※なお、一部の小区分では、書面審査区分も自分で選択できるケースがあります。
②第一次審査:5人の審査員によって絶対評価と相対評価がつけられる
次に、あなたの申請書は、原則5名の審査員へ送られ、第一次審査が始まります。
審査員は日本の大学など研究機関の研究者によって構成される「特別研究員等審査会」の専門委員(約1800人)が務めており、利害関係のある申請者の審査は行うことができないルールになっています。
一次審査では、申請書を複数の専門審査員が個別に読み込み、絶対評価により5段階の評点(5: 非常に優れている、4: 優れている、3: 良好である、2: 普通である、1: 見劣りする)が付されます。
その後、これらの項目評価を踏まえ、書面審査セット内での相対評価により5段階の総合評点が付されます。
③運命の分かれ道:採用内定orボーダーゾーンによる二次審査or不採択
第一次審査の結果に基づき、大きく以下3つの道に分かれます。
- 採用内定:総合評価が極めて高く、書面審査セット内で上位(採用内定数の80%程度)に入った申請者は、この段階で採用内定となります。
- ボーダーゾーンによる二次審査:採用のボーダーゾーン(採用定員の上下20%の範囲)に入った申請者は、二次審査に進みます。
- 不採択:残念ながら、上記以外の申請者はこの時点で不採択となります
④第二次審査でボーダーゾーン申請者の再評価を行う
一次審査で即採択されなくても、まだまだチャンスはあります。
二次審査の対象となるのは、一次審査でボーダーゾーンに入った申請書です。
そして、一次審査を担当した同一の審査委員が、他の4人の審査委員の一段階目の総合評価評点や審査コメントを参考にし、自身の評価を見直し、改めて評点を付します。
このプロセスにより、より多角的な視点から合否が慎重に判断されるのです。
(※参考:日本学術振興会「特別研究員・選考方法」)
学振の審査基準は客観的?何がどのように評価される?
審査員は、個人的な好みや印象ではなく、JSPSが定めた明確な「評定要素」に基づいて評価を行います。
評価の客観性を担保するため、以下の3つの柱で審査されます。
- 研究者としての将来性:学術の将来を担う優れた研究者となることが十分に期待できるか。
- 着想とオリジナリティ:研究課題設定に至る背景が示されており、その着想が優れているか、研究方法にオリジナリティがあり、今後の展望が示されているか。
- 研究遂行能力:研究を遂行する能力が優れているか。
申請書は、単なる研究成果の羅列ではなく、研究者としての資質や将来性を具体的にアピールすることが求められます。
特に、面接が廃止されたため、書面だけで審査員に意図が正確に伝わるよう、読みやすさや分かりやすさを意識して作成することが非常に重要です。
学振の評価結果は不採用者には開示され、採用者は開示請求で郵送取り寄せが可能
不採用者には、各審査項目の評点や該当する審査区分内での順位が電子申請システムで開示されます。
以下のような項目が確認可能です。
- 審査員の評点の平均値
- 総合評価のTスコア
- 非採択者の中のおおよその順位
- 同じ審査区分の申請者数、採択者数、非採択者数
なお、採択された場合でも、個人情報開示請求の手続きを行うことで郵送にて取り寄せることが可能です。
開示請求書のダウンロードや住民票の写し、手数料300円などが必要ですが、自身の申請書が審査員からどのように評価されたかを分析できます。
評価ポイントの参考になるため、取り寄せてみるといいかもしれません。
学振の評価表におけるTスコアとは?
Tスコアとは、学振の書面審査セット内でのあなたの相対的な位置を示す、偏差値のような指標です。
Tスコアは、総合評価を平均2.3、標準偏差0.6となるように補正した値として定義されており、自分の評価が全体の中でどのあたりに位置していたのかを客観的に把握できます。
なお、以下ページにて、学振審査結果詳細の画面サンプルが公開されています。一度確認してみましょう。
学振審査結果の自己分析方法
学振の審査結果は、自身の申請がどのように評価されたかを理解し、今後の研究活動や申請書作成に活かすための貴重な情報源です。
記載されている情報は限定的ですが、例えば以下3つの数値が書かれています。
- 研究計画の着想及びオリジナリティ(絶対評価)
- 申請書から推量される研究者としての資質(絶対評価)
- 書面審査セットにおける推奨度(相対評価)
スコアを確認することで、「研究計画の着想は評価されたが、研究者としての将来性の部分でアピールが弱かったのかもしれない」といった課題が見えてきます。
この自己分析が、次の申請や研究活動に活きる貴重な財産となるのです。
【まとめ】学振審査の方法と基準を知り、対策を立てよう
今回の記事では、学振の選考方法と審査基準について、具体的な仕組みから評価結果の分析方法まで解説しました。
審査員は必ずしもあなたの専門分野に詳しい研究者だけでなく、書面審査セットによってバランスよく組織された原則5名のチームで相対評価されます。
よって、専門外の人が読んでも論理的で分かりやすく、魅力や将来性が伝わる申請書を書く必要があります。
自身を「日本の未来を支える優秀な研究者になり得る人材」として、説得力をもってアピールする申請書を作成することが、採用への重要なポイントでしょう。
最後になりますが、学振の申請書を書き上げること自体が、研究者としてのスキル向上や研究活動の振り返りに繋がる側面があります。
事前準備と対策をしながら、ぜひ前向きに取り組んでみましょう!
「博士情報エンジン wakate」では、学振審査員経験者を招き、申請書の書き方セミナーなども行っています。
過去のセミナー情報は「学振申請書対策セミナーを開催しました」にて掲載しています。参考にしてみてください。

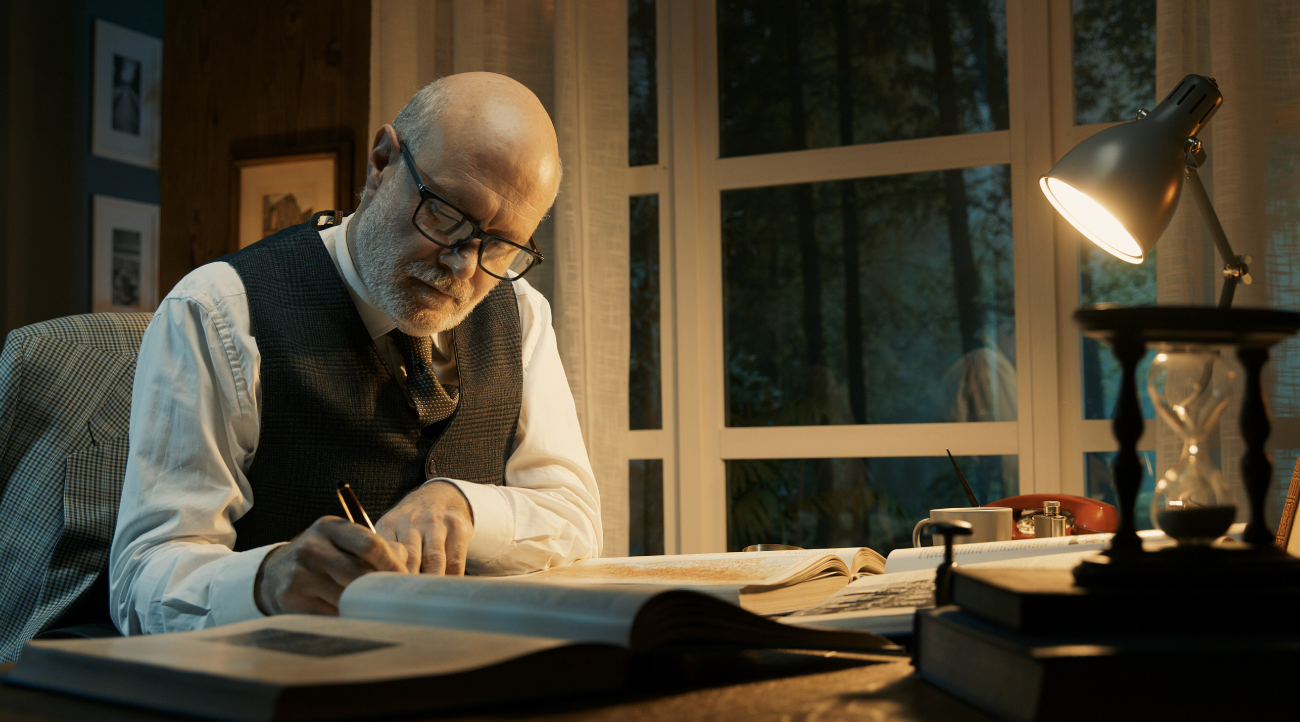


コメント